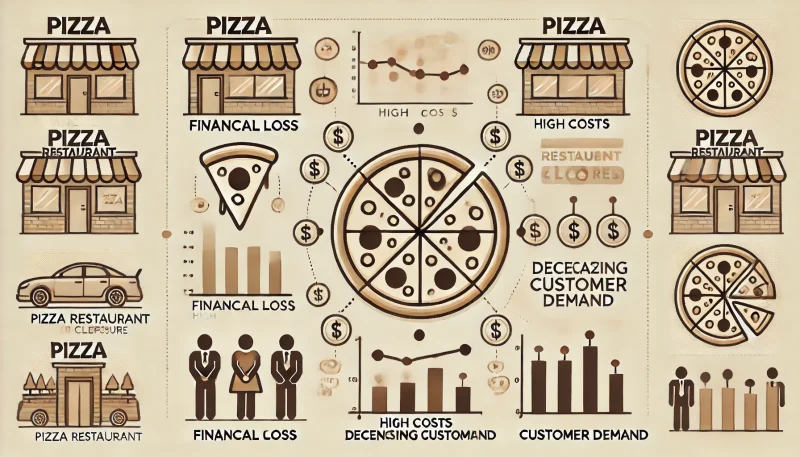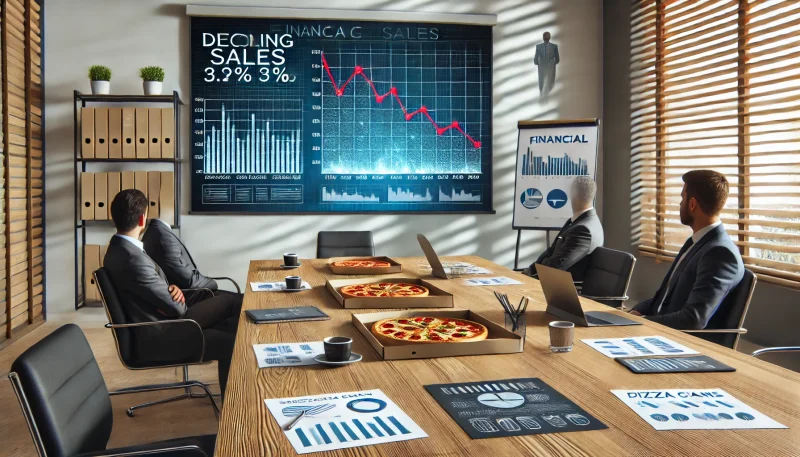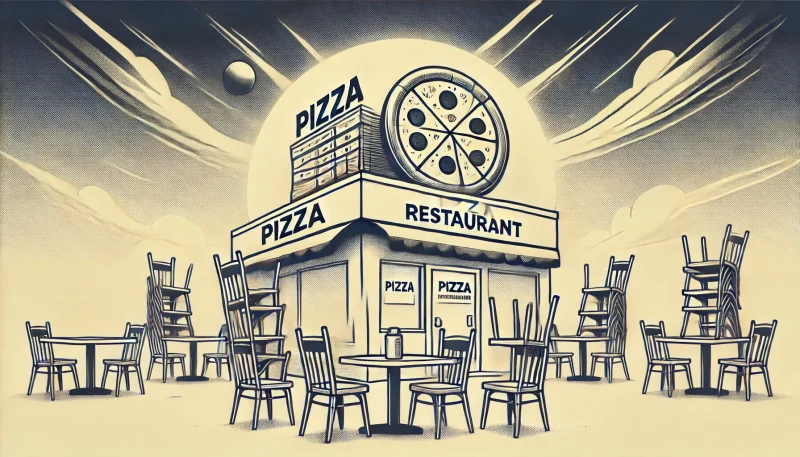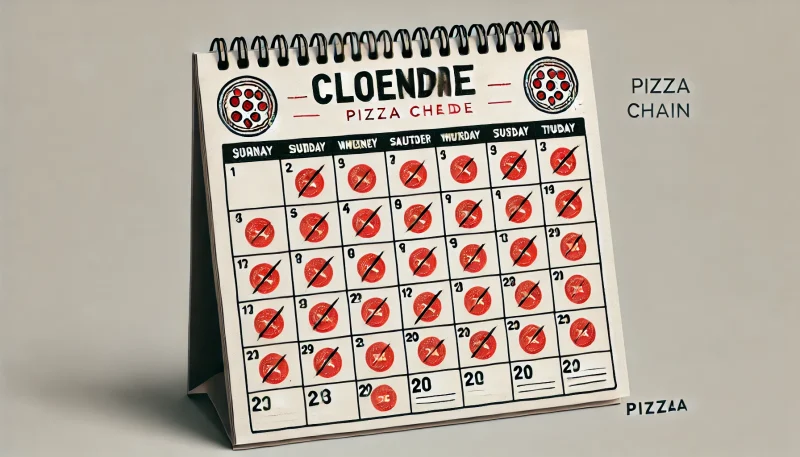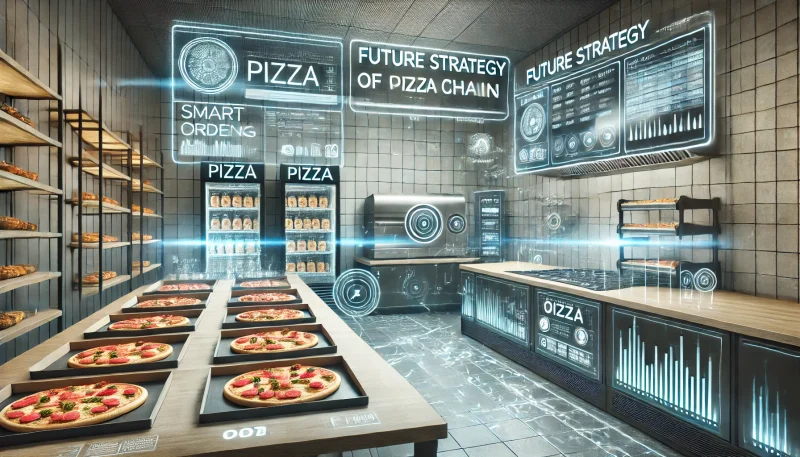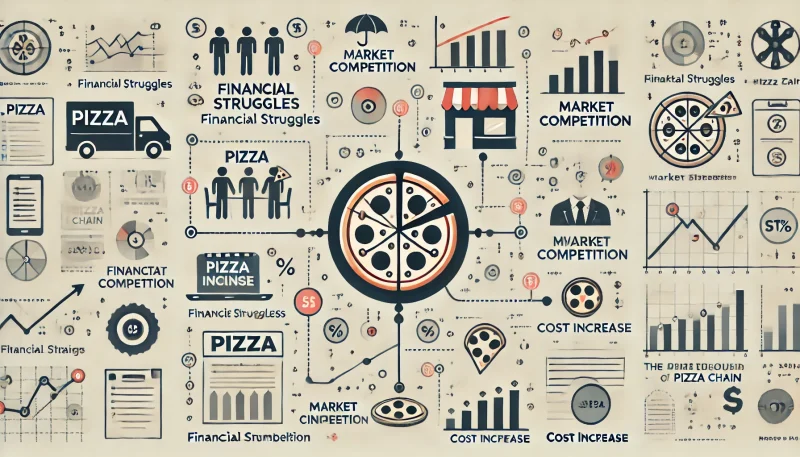ドミノピザが日本国内で172店舗の閉店を発表し、多くの人がその理由に関心を寄せています。
この記事では、ドミノピザが閉店する理由について詳しく解説し、背景にある市場の変化や経営戦略を説明します。
また、閉店一覧や対象となる店舗の特徴についても触れ、今後の事業方針を分析していきます。
急成長を遂げたドミノピザが、なぜ大規模な店舗閉鎖を決断したのか、その全貌を明らかにします。
この記事を読んでわかること
- ドミノピザが172店舗を閉店する具体的な理由や背景
- コロナ禍での急成長とその後の市場変化による影響
- 閉店対象となる店舗の特徴や地域の傾向
- 今後のドミノピザの経営戦略や事業方針
ドミノピザ閉店の理由とは?
- 閉店を決めた背景
閉店を決めた背景
ドミノピザが今回、日本国内の約2割にあたる172店舗の閉店を決定した背景には、複数の要因が絡んでいます。
その主な要因として、新型コロナウイルス禍における宅配需要の急増とその後の減退、経済環境の変化、競争の激化などが挙げられます。
コロナ禍による急成長とその反動
新型コロナウイルスが流行した2020年以降、多くの人が外出を控えるようになり、飲食業界全体でデリバリー需要が急増しました。この流れを受け、ドミノピザも積極的な店舗拡大を実施し、約400店舗を新規出店するなど急成長を遂げました。一時は全国で1000店舗を超える規模にまで拡大し、市場の拡大とともに売上も伸びていました。
しかし、2023年以降、コロナ禍が収束し、人々の外食需要が回復するにつれて、宅配ピザの利用頻度は減少しました。自宅での食事機会が減り、スーパーやコンビニで購入できる手軽なピザの人気が高まることで、ドミノピザの売上も影響を受けるようになりました。急成長の反動として、採算の取れない店舗が増えてしまったのです。
経済環境の変化によるコスト負担
また、経済環境の変化もドミノピザの経営に大きな影響を与えました。近年、原材料費や人件費、エネルギーコストの上昇が続いており、特に宅配業態にとっては、デリバリーコストの増加が大きな負担となっています。加えて、最低賃金の上昇や物流費の高騰により、利益率の確保が難しくなっていました。
こうした経済環境の変化に対応するため、不採算店舗を整理し、より効率的な経営体制を構築する必要があったと考えられます。特に、売上が伸び悩む地方店舗や、競争が激しい都市部の一部店舗は、閉店の対象となった可能性が高いでしょう。
宅配ピザ市場の競争激化
さらに、宅配ピザ市場の競争が激化したことも、閉店を決断する要因の一つでした。従来、宅配ピザは「注文して届けてもらう」ことが大きな強みでしたが、近年ではスーパーやコンビニで販売される店内調理ピザや冷凍ピザの品質向上が進み、消費者の選択肢が増えました。
特に、「ドン・キホーテ」「オーケー」「ロピア」といったディスカウントストアや食品スーパーでは、大型のオーブンで焼き上げた本格的なピザを低価格で提供し、消費者に支持されています。また、2024年8月には、コンビニ最大手のセブン-イレブンが宅配ピザ市場に参入し、さらなる競争の激化が予想されています。
このような状況の中で、ドミノピザは価格競争やサービスの差別化が求められるようになり、収益性の低い店舗を維持することが難しくなったと考えられます。
ドミノピザの閉店一覧と今後の動向
- どの地域の店舗が閉店対象なのか?
- 2025年までの閉店スケジュール
- 閉店による影響と顧客の対応策
- 今後の店舗戦略
どの地域の店舗が閉店対象なのか?
今回のドミノピザの閉店対象となる店舗は、全国の約2割にあたる172店舗ですが、特に地方都市や郊外の店舗が多く含まれると考えられています。都市部では一定の需要があるものの、地方では人口減少や競争激化の影響を受け、採算が取れなくなった店舗が増えました。
また、今回の閉店リストには、新型コロナウイルス禍の需要急増に合わせて開店した店舗が多く含まれています。これは、当時の巣ごもり需要が落ち着いた現在において、売上が大幅に減少し、維持が難しくなったためです。特に、近隣にスーパーマーケットやコンビニがあるエリアでは、これらの店舗が提供する手軽なピザ商品に需要を奪われるケースも増えています。
さらに、採算が合わない地域として、競争が激しい都市部の一部店舗も閉店の対象となっています。特に、複数の宅配ピザチェーンが密集しているエリアでは、価格競争やブランド間の顧客争奪が激しくなり、利益が確保しづらい状況になっています。そのため、これらの地域の中でも利益率が低い店舗が閉鎖されることになります。
2025年までの閉店スケジュール
ドミノピザは、今回の大規模閉店を段階的に進める予定です。2024年7月には最初の80店舗を閉鎖し、その後、2025年末までにさらに92店舗を閉店する計画となっています。このスケジュールは、従業員の雇用調整や物流の最適化を図るため、急激な閉店による混乱を避ける目的があります。
閉店対象となる店舗では、段階的な営業縮小が行われる可能性があり、例えば、営業時間の短縮やデリバリーエリアの見直しが実施されることが考えられます。また、既存の顧客に対しては、近隣の営業店舗への誘導を行い、利用の継続を促す施策が取られるでしょう。
一方で、DPE(ドミノ・ピザ・エンタープライズ)は、閉店によるコスト削減を年間約15億円(1550万豪ドル)と試算しており、今後は収益改善が期待できる地域への投資を強化すると発表しています。このため、閉店と同時に、新たな形態の店舗を展開する可能性もあります。
閉店による影響と顧客の対応策
今回の大規模閉店により、最も影響を受けるのは閉店対象店舗の従業員と、これまでその店舗を利用していた顧客です。特に、閉店する地域では、ドミノピザの宅配サービスを利用できなくなる可能性があるため、顧客は代替手段を模索する必要があります。
ドミノピザは、閉店による影響を最小限に抑えるため、既存の店舗ネットワークを活用し、閉店店舗の顧客を他店舗へ誘導する施策を進めると考えられます。また、一部地域ではデリバリー拠点の統廃合を行い、デリバリーエリアを拡張することでサービスの継続を図る可能性もあります。
さらに、ドミノピザはデジタル戦略を強化し、オンライン注文の利便性を向上させることで、より広範囲の顧客に対応する方針を打ち出しています。例えば、アプリやウェブサイトの機能改善、配達時間の短縮、キャンペーンの充実などが検討されていると考えられます。
ただし、一部の顧客にとっては、閉店によって宅配ピザの選択肢が減るため、競合他社へ流れるケースも増えるかもしれません。そのため、ドミノピザは価格競争やサービス向上によって、顧客離れを防ぐ対策を進めることが求められます。
今後の店舗戦略
ドミノピザは、今回の大規模閉店を通じて、事業の再構築を進める方針です。これまでのような積極的な出店戦略ではなく、採算性の高い店舗に投資を集中させる「選択と集中」の戦略へとシフトすることが予想されます。
まず、都市部や需要が高いエリアでは、既存店舗の設備投資を強化し、サービスの質を向上させる可能性があります。例えば、最新のデリバリー技術を導入し、注文から配達までの時間を短縮することで、競争力を高める施策が取られるでしょう。
また、デジタル化を推進し、アプリやオンラインサービスの利便性を向上させることも戦略の一環と考えられます。近年、モバイルアプリ経由での注文が増加しており、アプリの使い勝手を向上させることで、リピーターの増加を狙うと考えられます。
さらに、新たな業態として、小型店舗やテイクアウト専門店の展開も視野に入れているかもしれません。これにより、従来の大規模店舗よりもコストを抑えつつ、需要のあるエリアでの販売を強化することが可能になります。
加えて、競争が激化する市場において、他社との差別化を図るため、オリジナルメニューの開発や新たなプロモーション戦略も検討されるでしょう。特に、健康志向の高まりを受けて、低カロリーやヴィーガン対応のピザなど、新たなターゲット層を意識した商品展開が期待されます。
このように、ドミノピザは単なる閉店だけでなく、今後の成長に向けた戦略を同時に進めることで、事業の安定化を図ると考えられます。競争が激化する宅配ピザ市場において、どのようにポジションを確立していくのか、今後の動向が注目されます。
まとめ:ドミノピザの閉店理由について
この記事のポイントをまとめます。
新型コロナ禍での宅配需要の急増により急成長した
コロナ禍収束後に外食需要が回復し宅配需要が減少した
短期間での急拡大により不採算店舗が増加した
原材料費や人件費、物流費の高騰が経営を圧迫した
地方都市や郊外の店舗が採算を取れず閉店対象になった
競争激化によりスーパーやコンビニのピザ販売が脅威となった
2024年8月にセブン-イレブンが宅配ピザ市場に参入する
価格競争の影響で利益率が低下した店舗が増えた
フランチャイズ加盟店の経営負担が増し閉店を決断したオーナーもいた
2024年7月に80店舗、2025年末までに92店舗が閉鎖予定
一部店舗は営業時間短縮やデリバリーエリア縮小を実施した
今後は収益性の高い地域への投資を強化する方針を発表した
既存店舗のデジタル化や注文システムの改善が進められる
低コストで運営可能な小型店やテイクアウト専門店の展開も視野に
業態転換と競争力強化が今後の成長の鍵となる